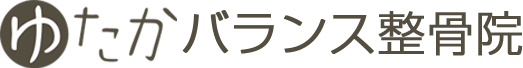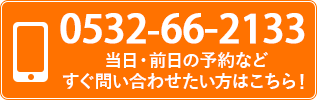鼠径部の痛み、もしかしたらグロインペイン症候群かも
2022年12月13日

カラダのコラムを読んでいただきありがとうございます!
今回はスポーツ障がいであるグロインペイン症候群について、状態とその予防について書かしていただきます。
スポーツをやっている子供、保護者、指導者全ての人が知っておくと役立つと思うので、是非最後まで読んでいただけると嬉しいです!
それではさっそくやって行きます。
目次
はじめに
最近ではスポーツ人口は年々増加傾向にあります。
それに伴いスポーツ障がいも増えておりセルフケアが重要視されています。
ですが、セルフケアと言っても何をして良いかわからないですよね…
ここでは定期的にスポーツ障がいを1つずつ取り上げてその予防からセルフケアまでご紹介させていただきます!!
今回は股関節、鼠蹊部に痛みを訴えることが多いグロインペイン症候群についてやって行きます。
グロインペイン症候群とは
グロインペイン症候群とは鼠蹊部痛症候群とも言われていて、特にサッカーなどの走る、蹴る、捻る動作の多い競技で起こりやすくなっています。
原因
筋力バランスの低下や過剰なトレーニングにより股関節周辺の炎症などが原因となってきます。
大腿部の筋肉はかなり強い力を持っているため、繰り返しストレスがかかると、炎症を起こしたり骨が剥がれてしまい、痛みが出てきます。
予防
予防としては
- 運動前後の股関節のストレッチ
- ケガの後、完治してないのに無理にプレーを続けない
- 股関節周囲の筋力強化
- 筋肉の協調性を高める
などがあります。
ストレッチについて
上記でもあるように予防法には股関節周りの柔軟性が大切になってきます。
そのためのストレッチを少しだけ紹介して行きます。
※下記で紹介するストレッチはグロインペイン症候群のみならず全ての人に有効です。
ストレッチは大きく分けて2つあり
①動的ストレッチ
②静的ストレッチ
があります。
①動的ストレッチ
動きながら反動をつけてストレッチする方法で部活動などで行うブラジル体操などのことです。
動きながら行うことで心拍数向上や運動の切り替えがスムーズになるなどの効果があり、運動前のストレッチに効果的とされています。
②静的ストレッチ
筋肉を伸ばした状態で反動をつけず、一定時間保持するやり方です。
一定時間保持することで筋肉の緊張を和らげ、柔軟性の向上や可動域の拡大などの効果が得られます。
そのことから静的ストレッチは運動後のストレッチに良いとされています。
※静的ストレッチは運動前に行うと、必要以上に可動域や柔軟性が向上され筋発揮の低下やパフォーマンスの低下に繋がってしまうこともあるため、準備運動には動的ストレッチを用いることが多くなってきます。
グロインペイン症候群のセルフケア
セルフケアとしては股関節周囲筋のストレッチと協調性の向上を目指すのが大切になっていきます。
今回はいくつかある中で3つ紹介して行きます!!
腸腰筋ストレッチ

股関節の前面のストレッチはゆっくりと伸ばして行き10秒ほど止めてゆっくり元の位置に戻ります。
これは運動後のストレッチとして行うのがおすすめです!
振り子運動


手は壁につけ、足を前後に振り子のような運動をします。
回数は左右10回を2〜3セット行います。特に運動前には入念に行いましょう!
上半身と下半身の協調運動


先ほどの振り子運動のように前後に動かすとともに、上半身も同時に動かし下半身との協調運動を行います。
回数は左右10回×2セットほど行います。これも運動前に行うのがオススメです!
最後に
グロインペイン症候群はサッカーなど、股関節周辺の動きが多いスポーツなどでは非常になりやすいため、股関節周りのストレッチは痛みが出る前に練習前後で行うように心がけておきましょう!
ゆたかバランス整骨院では、スポーツを行なっている小学生〜大人まで幅広い年齢層の方にお越しいただいております。
手技はもちろん電気や鍼施術も行っており、少しでも早くスポーツ復帰できるようサポートさせて頂いてます!
体のことでお困りのことがあれば是非一度ご相談下さい!
https://yutaka-seikotu.com/contents/sports/
スポーツ障がいのページはこちらから↑